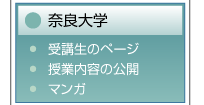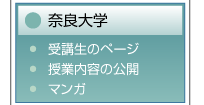ライブの魅力
とある講演会でこと。例によって「過分」な講師に対する紹介のあと、司会者は「『万葉集』は日本人の心の故郷」とさかんに『万葉集』を持ち上げていた。『万葉集』は日本人の心の故郷、飛鳥は日本人の心の故郷とボルテージは上がるばかりである。たしかに、講演者であるわたしに期待されているのは、こんなところであろう。へそ曲がりのわたしはそんな結論が出ているのなら、講演を聞かなくてもと、意地悪な気持ちになったりする。けれども、かけ出しの研究者であるわたしを招いてくれる講演会は、見識のある企画と考えることにしているので、日程さえあえば断らないのを建前にしている。それに何といっても、聞き手の反応が手に取るようにわかるのが魅力である(もちろん、正直にいうと経済的魅力もある)。これは学会の研究発表でも同じで、研究の成否が拍手でわかるときがある。もちろん、常にうまくゆくとは限らないから、研究発表が終わって自棄酒(やけざけ)ということも、ままある。論文にしろエッセイにしろ、読み手に対面するわけではないので、じかに反応を知ることはできない。だから、講演会・口頭研究発表会のライブの魅力は、捨てがたいものがあるのである。
北国の春
わたしの拙い話を聞いて、涙した人がひとりいる。あとにも先にも、ただひとりである。それは、中国・蘇州大学の日本語学科のある女子学生である。話は昨春にさかのぼる。蘇州大学で行なわれた国際研究集会のあと、日本語学科の特別授業を頼まれた折りの話である。中国でもカラオケが大ヒットした「北国の春」を題材にして話を進め、この歌が出稼ぎ者の望郷歌であることを枕にして、『万葉集』の望郷歌について、話をしていた時のこと、女子学生のひとりが涙を流し、それが伝染したらしく、教室は異様な雰囲気に包まれてしまったのである。話をしていたわたしは、講義の何に反応して泣いたのかも判らず、ただおろおろするばかりで、結局は早めに話を切り上げてしまった。聞けば、最初に泣いた女学生は、中国の内陸部の貧しい農村出身の学生であるが、一族の期待を集めて、先進地域のこの蘇州大学に進学し、その夏卒業ということであった。ところが、もうひとつお目出度いことが彼女には重なっていた。彼女は卒業と同時に結婚するのだという。それならば、涙は無用と思うが、卒業して故郷の寒村に戻るという両親との約束は、同級生との結婚で反古になってしまうというのである。しかし、よく考えてみると、彼女はわたしの話に感動したのではなくて、自分の身の上を思い出して泣いたのである。これまた、何とも妙なオチがついてしまったが、卒業後は蘇州の紡績工場の外弁(外国との交流を促進するセクション)に就職が決まっているということであった。
ふたつの故郷
その授業でわたしが言ったのは、次のようなことである。万葉時代の貴族というものは、原則としてふたつの故郷を持っている。一つは京の中にある邸宅であり、もうひとつは先祖から引き継いだ氏族の根拠地である。おそらく、一方の故郷にいるときには、一方の故郷をいとおしく思ったはずであり、大伴坂上郎女は大伴氏の根拠地である跡見庄(桜井市・外山付近か)を「故郷」と歌に表現しながらも、「故郷」にいるときには平城京の邸宅に残した娘に思いをはせる歌を残している(『万葉集』巻四の七二三・七二四)。『万葉集』の時代に生きた人びとは、こういったふたつの故郷のはざまに生きた人びとであり、それは古今東西の都市生活者の宿命といわなければならない。古代都市・平城京もこういったふたつの故郷を持つ人びとが集まった都であった。かえりみて、千昌夫の「北国の春」のヒットは、日本の高度成長と東北からの出稼ぎという背景を抜きに考えることはできない。ここに都市生活者の望郷の文学ということを、考えねばならない。おそらく、涙を流した女学生は、大学での勉強を出稼ぎのごとき感覚で見ていたに違いない。中国においての大学教育とは、われわれが考えているよりも、もっと重いものであり、父母と一族は言うまでもなく、彼らの肩には国家の期待も重くのしかかっているからである。
生活と心情
『万葉集』の歌の担い手の第一は、平城京に生きた官人たちである。彼らはふたつの故郷をたくましく生きた人びとであったと、わたしは現在考えている。万葉時代の法律である律令の中には、平城京内の官司の勤務者の農作業の規定がある。春と秋の農繁期には、「田暇」(でんか)と呼ばれる十五日間の休暇が与えられていたのである。この規定でおもしろいのは、一斉に田暇を取ると役所の機能が停止してしまうので順番に休むことや、田のある場所で農作業の開始時期が異なることを考慮に入れて、弾力的にこの条項を運用して個別に休みの期間を定めることが、条文に歌われている点である(養老暇寧令 第一条)。平城京内に邸宅を構える貴族であっても、農繁期には、その根拠地に赴いたことは万葉歌が証明するところであり、こういった京と故郷の往復が、万葉びとの生活を支えていたのである。ところが、平城京で生まれ育った世代には、平城京を故郷として意識することを、これまた万葉歌によって跡付けることができるのである。
つまり、『万葉集』には、古代都市生活者の文芸という側面もあるもあることを、忘れてはならないのである。 |