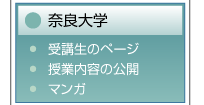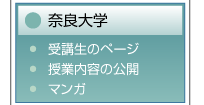憂欝な季節
東京から奈良に赴任して、四回目の春を迎えた。奈良大学で『万葉集』を研究しているわたしにとって、うれしい悲鳴をあげる季節がある。それは、春と秋の行楽シーズンである。というのは、東京の大学に籍を置いていたせいで、東京には友人や世話になった教授がたくさんおり、この悪友と敬愛すべき恩師が堰(せき)を切ったようにやってくるのが、この季節だからである。最近は、ファックスという便利なものができて、徳利と杯を描いた絵でわたしを呼び出す悪友もいる。左党のわたしには断りがたい悪魔のささやきである。最悪なのは正倉院展のころで、学生時代に戻って悪友と飲み明かす日が連続してしまう。時には、自分の研究室で学んでいる留学生を東京駅から新幹線に乗せ、自分は東京駅から奈良の拙宅に電話をかけてきて、忙しいから一週間預かってくれというような、猛者(もさ)もいる。そんなけしからんやからには、次に会ったときの酒代は三次会まで全額持たせることにしている。
余談となるが、こんな時にありがたいのは、奈良町の古い旅館で、留学生のふところ具合に合わせてのサービスが、何ともうれしい。パンの耳をかじっても、世界文化遺産・法隆寺を見たいというアジアの留学生もいるからである。その旅館の女将は心得たもので、素泊りにして自炊させてくれるので、預かったわたしとしても安心なのである。お世辞にもきれいな旅館とはいいがたいが、何の嫌味も言わずそんなサービスの提供がある旅館は、留学生にとっても、わたしにとっても心強い存在である。
ヒンコンナブンカザイギョウセイ
そんなアジアからの留学生の古寺巡礼は、思わぬ発見をもたらしてくれることもある。ここでは仮にA君としておこう。A君を法隆寺に連れてゆき、昼食ににゅう麺を食べたあと、A君は言いづらそうな顔をしながらも、わたしに次のようなことを言った。それは「ヒンコンナブンカザイギョウセイ」という言葉てあった。流暢な日本語ではあったが、わたしは彼の言った「貧困な文化財行政」という言葉の意味を解するまで数分を要してしまったような気がする。A君としても考えあぐねての言葉であっようだ(と同時に、彼の語彙力には感心した)。A君は言う「日本国政府は、なぜ世界文化遺産・法隆寺の建物のペンキの塗り替えを怠っているのか!」と。中国系である彼は、お寺の柱は朱塗りと決まっていて、仏像には金箔がはられているものであり、それからすると法隆寺は「荒廃の極み」であると言うのである。すべてを呑み込んだわたしは、次に西の京・薬師寺に彼を案内することにした。
「日本美・再発見」の再発見
薬師寺に着くと、A君はわが意を得たりという表情で、昭和五十一年に再建なった金堂の朱塗りを見ていた。ところが、A君はつかさず「あの汚い塔には、なぜペンキを塗らないのか」と聞いてきた。A君の言う「汚い塔」とは、国宝・東塔のことである。わたしは、哀調帯びた「木肌の美」や「木目の美」を説いたが、ついにA君の疑問は解けなかったようである。もし、薬師寺の東塔や法隆寺の伽藍を元どおり朱塗りにして復元しようと誰かが発案すれば、たぶんそれは一笑にふされるであろう。それこそ「祖先の偉業」と「日本美」とを冒涜する蛮行といわれるかもしれない。
そこで、わたしは研究室に帰るとA君に伊勢神宮の写真を見せることにした。彼は写真を一見すると「これはいつ完成するのか」と聞いてきた。彼に言わせると、伊勢神宮は壁が未完成で、ペンキも塗り忘れているのだという。わたしはここではたと考え込んでしまった。われわれが「日本美」といっているものは、従来から「美」といわれているものを過去の言説によって追認しているだけで、これは一種の思考停止に等しいかもしれない。今度、A君にあったら、金閣寺と伏見稲荷に連れてゆこうと思う。日本にも朱と黄金の文化はあるのだと・・・。
イメージを固定化するこ との危険性
しかし、考えてみると飛鳥・藤原・平城京に林立した古代寺院の柱には朱が塗られ、仏像には金箔がはられいたのである。けれども、いつの日か剥げた朱を塗らなくなり、仏像の金箔のはりかえもしなくなったのである。もし、これを「日本美」であるというなら、ここに日本美なるものが発生したと見ることができよう。しかし、その「美的感覚」は同じアジアの人びとにも共有されるものではなかったのである。中国やタイの寺院を訪ねれば、それは一目瞭然である。朱塗りの柱に金色の仏像に、われわれ・日本人はむしろ違和感を覚えてしまうからである。
毎年四月、大学で『万葉集』の講読をはじめる時に、口を酸っぱくしていうことがある。『万葉集』に登場する飛鳥は清らかな山河であり、われわれはそこから田園風景を想起してしまうが−、実際の景観はそうではない。古代の飛鳥は、朱塗りの寺院と金色の仏像が輝く、周辺とは隔絶した空間であり、莫大な投資が行なわれたいわば当時のハイテク都市と見なければならない。むしろ、なぜそのハイテク都市「飛鳥」が、万葉びとの心の「故郷」として歌には表現されるのか、そのギャップこそ考察の対象にすべき事項である。そう、わたしは説くことにしている。それが、わたしの『万葉集』四月開講の第一声である。もちろん、パンの耳をかじって大和の古寺巡礼を果たし、枯淡の「日本美」に反問したA君の言葉で講義がはじまるのは、いうまでもない。 |