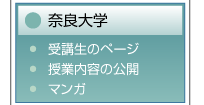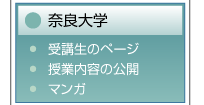万葉の春
恩師・桜井満が、よく揮毫した言葉がある。それが「万葉の春」である。その桜井教授は、立春の前に逝ってしまった。端的に言えば、『万葉集』は春の歌集であるというのも、桜井教授の言葉であった。『万葉集』四五一六首。巻一の巻頭である国歌大観番号一番歌は、雄略天皇の御製歌であり、それは若菜摘みの<うた>である。
一番歌に対して、『万葉集』巻二十の巻末歌、つまり最後の歌も初春の雪をうたう大伴家持(おおともの・やかもち)の作品である。
三年春正月一日、因幡国庁にして、饗を国郡の司等に賜ふ宴の歌一首
新(あらた)しき年の始の初春の今日降る雪の いや重け吉事
上の一首は守大伴家持作れり (巻二十の四五一六)
天平宝字三年(七五九)の正月、家持の赴任していた因幡の国庁には、雪が降ったのであろう。新年の雪は吉祥(めでたいしるし)である。家持はうたう。年の始めの今日降っている雪のように、いよいよ重なれ、よいことが−と。
春に始まり、春で終わる
春で始まり、春で終わる歌集。それが『万葉集』なのである。もちろん、これは偶然ではない。編纂者の意図によって、四五一六首の冒頭に据えられ、四五一六首めの歌集の閉じ目に据えられているのである。簡単に言ってしまえば、「祝福」の意味が込められている。祝福をせんがために、冒頭に終末にこれらの<うた>が、置かれているのである。
永遠の祝福
「来年はよい年に、来年はよい年に」と思いながら、人は年を重ねてゆく。また、来年はよい年に、来年はよい年にという人びとの願いをよそに、歴史は進んできたのであろう。おそらく、終末歌である家持詠はこの歌集をひもとき、この歌集に学ばんとするすべての人びとに対する祝福であるといえるのである。
ふたつの未来観
ところで、これは解剖学者の養老孟司さんの言葉だが、近代科学を誤って理解している人は、時として明日のことが予測できるかのごとき幻想を持ちやすいという。どんに精緻な理論をもってしても、予測は予測でしかないということを、人はついつい忘れてしまう。震災もそのひとつであると養老さんはいう。
とすれば、われわれに残されているのは、ふたつの生き方だろう。ひとつは、世の中に常なるものはない。だから、無常の世の中を生きるのに重要なのは、ある種の諦(あきらめ)であり、そういった「諦観」(ていかん)を早く自分のものにすべきであるという考え方である。鴨長明や吉田兼好のような中世の隠者の思想である。
もうひとつの生き方は、予測できない未来なら、それがよきものであることを願おうという生き方である。もちろん、家持の「いや重け吉事」という言葉での祝福は、この未来観に近い。「祝福」か「諦観」か。年の初めに−こたつでみかんでも食べながら−このふたつの人類の知恵について考えてみようと思う。 |