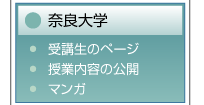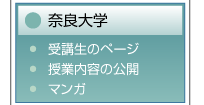天国の改造
この春、「第一回中日文化比較研究国際学術研討会」という研究集会に参加した。主催は蘇州大学中日比較文化研究所で、三月二十五日から二十九日まで、同大学で行なわれた。年配の方なら、蘇州といえば渡辺はま子が歌って一斉を風靡した「蘇州夜曲」を思い出すかもしれない。この歌で水の都と讃えられた蘇州に対して、蘇州人は次のような言い回しを好む。天に天国があるなら、地には蘇州と杭州があるさ。中国人が天国にも例える理想の地の一つが、蘇州なのである。しかし、天国にも再開発が必要らしく、街は高層ビルの建築ラッシュに沸いていた。ところが、この光景に私は何だか不思議な懐かしさを感じてしまった。はじめてなのに妙に懐かしいのである。瓦礫の山の隣のビル、もっこを担ぐ人々の小走り。不思議な懐かしさはこの辺りから来るようだ。そうだ。これは高度経済成長期の日本では何処にでもあった光景である。天国にも再開発の波が押し寄せていることを知った私は、この改造進む天国での研究集会・シンポジウムに臨んだ。
日本人の研究者に対する批判
まず、研究集会は中日比較文化研究所長主任・梁継国氏の基調演説からはじまった。この中で印象に残ったのは、従来の日本と中国の比較文化研究に対する批判である。日本人の中国文化研究が、ややもすれば日本文化のルーツ研究に過度に傾斜していないかという問いは、日本人研究者には少し耳の痛いところである。梁氏はその返す刀で、韓国における日本文化研究にも次のような批判を加えた。韓国の日本文化研究は、日本文化のルーツを朝鮮半島の文化に結びつけ過ぎているのではないか。私にはこの二つの問いが、たいへん興味深いものに映る。それは、川を遡って源流を究めるというような発想法で文化を考えることの限界を教えてくれるからである。さらには、比較文化研究の持つ、危険性のようなものを、私はこの講演から学んだような気がするのである。東アジアにおける比較文化研究が、大東亜共栄圏構想を正当化・合理化するために利用されたという失敗の歴史が、すでにあるからである。東アジアにおける比較文化研究は今後さらに重要度を増すであろうが、ルーツ追求型の研究に潜む民族意識の起伏には注意が必要であろう。東アジアの比較文化研究の科学的・実証的な方法が確立されることが、急がれるのである。
日中研究者のすれ違いと空振り
二十五日の午後から行なわれた分科会では、五十名近い日中の研究者が、「言語文化分化会」「文学文化分化会」「人文・宗教・教育文化分化会」の三分科会に別れて、研究発表と討論を行なった。私が参加したのは文学文化分化会で、二日間にわたり熱心な討論がなされたのが印象的であった。九人の発表者が一人持ち時間を一時間として、発表を行なったのであるが、熱心な討論の前に時間が足りるはずもなく、十一時間に及ぶ意見交換がなされた。こういった長い討論を成し遂げたという満足感はあるのだが、その反面、なにかこの討論がすれ違いに終わっていないか気になるところがある。文学文化分化会は日中双方の文学研究の現状を踏まえて、その比較を行なうセッションなのだが、中国側の研究者の関心は日本の近代文学の形成過程にあり、日本側の研究者の関心は主に中国の古典世界にあって、討論の方向が定まらなかったといえよう。
中国側が日本の近代と現代に深い関心を示したのに対して、日本側は中国の過去の文化遺産に傾斜して、討論を組み立てようとした感がある。これには、二つの理由があるように思われる。一つめの理由としては、この研究集会の呼び掛け人である中日比較文化研究所長主任の梁継国氏が、『万葉集』の研究者であり、日本から古典研究者が多く招聘されていたことがあげられよう。しかし、理由はそれだけではなさそうである。中国における日本文学研究の大部分が近・現代文学に集中していることも、その原因の一つであるとみることができる。たしかに、日本語の習得そのものが難しいのだから、研究の関心が古典に向かうことは少ないのは当然といえば当然である。また、日本の文学は中国の文字や文学を学ぶところから出発しており、日本の研究者の関心が過去に向かうことはやむを得ないことであろう。しかし、欧米の日本学研究者が古典研究の上でも優れた業績を上げている現在、中国における日本文学研究が著しく近・現代文学に集中していることは、注意しなければならない事実である。このほか、中国の日本文学研究の中心が未だに紹介や翻訳中心であることも明記しておく必要があるだろう。もちろん、これは傾向を述べただけであり、本年度の上代文学会賞が胡志昂氏(上海・復旦大学教員)に決まるなどの快挙もある。
これに対して、日本人研究者の関心がもっぱら中国の古典世界に向いていたことも、注意しなければならない。もちろん、東洋史などでは世界の研究をリードしている日本なのであるが、こと日本人の日本文学研究者の関心は、中国の古典世界に集中しているといっても過言ではない。近代以前においては学問といえば、漢籍を学ぶことであったことを考えると、当然といえば当然なのだが、中国の近・現代に対する関心が薄いことにも驚かされる。
こうして、われわれの分科会の討論は時にすれ違い、時に空振りとなることも、多かった。聞けば他の分科会についても、同じような状況であったという。討論の為の土俵作りがなされていなかった結果であろう。その意味では、今回の研究集会は失敗であったかもしれない。しかし、今回の研究集会の最大の収穫は、この「すれ違い」「空振り」にあると、私は現在ひそかに考えている。それは、「すれ違い」「空振り」を通して、互いの研究の視点の違いを、日中の研究者が認識することができたからである。「中日比較文化研究」といっても、中日の研究者の関心はこうも違うものかと、感じ取ったのは私だけではなかったと思う。対話とか交流というものは、たぶんこういった互いのギャップを認識し合うことから始まるのものなのだろう。
成長期の思想を模索する中国
シンポジウム終了後、訪れた蘇州城外の寒山寺には、日本人の観光客が溢れていた。日本人観光客は争って、鐘楼に登り鐘をつく。有名な張継の漢詩「楓橋夜泊」に登場する鐘声、すなわち「夜半の鐘声客船に到る」の鐘をつくのである。もちろん、鐘は近代のもので張継の時代のものであるはずもない。しかし、かの有名な寒山寺の鐘をついて帰ることが、何よりの土産話になると、実は私も考えたのである。お別れのレセプションでは「日本の学者は古典趣味。中国の近・現代を見てほしい」と皮肉くられたが、むべなるかなである。その寒山寺からの帰り道、再開発進む街を通り抜けたくなり、バスから降りたのだが、そこには、冒頭に述べた妙に懐かしい風景が広がっていた。中国式ではあるが、久しぶりにヨイトマケも見た。こちらは天国の改造に余念がないようだ。さらに歩くと、道端で露店に出会う。海賊版とおぼしき酒井法子のカセットが目についた。見れば、これもまた海賊版とおぼしき日本の小説や漫画が山のように積まれている。
中国側の研究者が日本の近代化をことさら問題にするのは、中国における成長の思想のようなものを、日本の近代に模索するためではないか。そういえば、つい最近まで日本の学者の大きな仕事は、外国の理論の紹介であった。とにかく、成長に役立つものは何でも吸収しよう、有り体にいえば成長期の思想とはそんなものだ。成長、そのものが絶対にプラスの価値であるとすれば、それに寄与するものは何でも取り入れる。成長に必要ならば天国も改造する、そういう屈託のない底抜けに明るい成長期の思想に、この研究集会で、久しぶりに出会うことができた気がする。
中日比較文化研究の発展のために
中国悠久の歴史に学ぼうとする日本人研究者と、成長期の思想を模索する中国人研究者。ギャップがあるのは当然である。「すれ違い」「空振り」の理由を自分なりに納得しようとして、以上のような自己分析をしてみた。東アジアの比較文化研究は常には、過去の不幸な歴史からデリケイトな問題がある。とくに、比較文化研究は民族意識とあいまって、政治的利用をされやすい。それだけに、比較文化研究の確固たる方法の確立が、いち早く求められる気がしてならない。わたしはその第一歩として、対話と交流が必要なことは認めるのだが・・・、問題はむしろその後ではなかろうか。それは「すれ違い」「空振り」の理由を、互いがじっくりと考えることだろう。標語にしてしまうと、薄っぺらなまとめとなるが、「すれ違いと空振りに学べ」−これが、この研究集会に参加しての最大の収穫である。 |