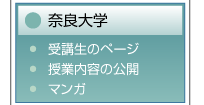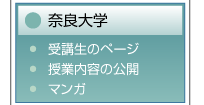橡(つるはみ)の くぬぎ染めの
解き洗ひ衣の 洗い張りした衣を
怪しくも 我ながら不思議なほどに
ことに着欲しき むしょうに着たい――
この夕かも この夕べ・・・やっぱり、古女房が俺には一番
(譬喩歌 衣に寄する 巻七の一三一四)
生活の機微
現代生活には、現代生活の機微というものがあり、古代生活には古代生活の機微というものがある。長旅に疲れて帰ってきた後、洗濯物をすべて干し終えると、私は何ともいえない気持ちになる。それは、秘かな悦び、小さな幸福といでもいうべきものか? これは私個人の生活体験であり、個のなかに芽生えた気持ちである。けれども、このことを友人に話すと、皆うなずいていた。では、なぜそういった個人的体験が、時として共感を呼び、共有されるのか? それは、個々の生活体験であったとしても、多くの人々が共有できる生活の機微に触れる心情だからであろう(「そうそうあるあるそういうこと・・・」という共感)。
わが万葉研究の目指すところは、万葉びとの生活の機微と、歌との回路を解明するところにある。よく人は私のことを、折口信夫を始祖と仰ぐ民俗学派の四代目という。しかし、一度として私自身は看板にこだわったことはない。生活と歌表現の回路を見つけるために、民俗学や歴史学、考古学の成果をできるだけ取り入れたいと思っているだけである。
洗濯と恋のはじまりと
この世を生き、そして死んでいった女たちは、一生にいくたびもこう嘆息したことだろう。死ぬまでに何度食事を作り、何度洗濯すればいいのかしらと。何度、同じことを・・・と。私は、『古事記』の話や万葉歌を、切り取られた生活史の一齣と考えて、その機微を明らかにできたらと今日も思案する。
洗濯をする女性を天皇が見初めるという話が、『古事記』にある。「衣を洗う」ということの文献上の初見は、実は『古事記』にあるのである。雄略天皇は、三輪川(美和河)で、引田部赤猪子(ひけたべのあかゐこ)を見初めている。つまり、洗濯をする姿を見て、その容姿を気に入ったのである。これを理解するためには、洗濯という労働が、半裸の労働であったことを想起する必要があるだろう。
亦、一時(ひととき)に、天皇遊び行きて、美和河に到りし時に、河の邊に衣を洗ふ童女(をとめ)有り。其の容姿(かたち)甚麗(いとうるは)し。天皇、其の童女を問ひしく、「汝(なむじ)は、誰が子ぞ」ととひき。答へて白(まを)ししく、「己が名は、引田部赤猪子(ひけたべのあかゐこ)と謂ふ」とまをしき。爾(しか) くして、詔はしむらく、「汝は、夫に嫁(あ)はずあれ。今喚(め)してむ」とのりたまはしめて、宮に還り坐(ま)しき。
(『古事記』下巻)
女たちは愛する者のために衣を洗い、時として衣を洗う水辺で見初められ、恋に落ちたのであろう。この物語は、そういう女たちの生活史の蓄積の上に成り立つものなのであろう。
橡の解き洗ひ衣
冒頭に挙げた歌は、巻七の「衣(きぬ)に寄する」に収載された歌の五首のうちの一首。橡(つるはみ)はクヌギのことである。万葉の時代、そのドングリの煎じ汁を使って染色が行われていた。黄褐色に染めるときには、橡(つるはみ)すなわちクヌギが使われていたようである。この橡染めは広く愛用されていたことが、巻七の「衣に寄する」の冒頭に収載された歌からわかる。
橡の 衣は人皆 事なしと 言ひし時より 着欲(ほ)しく思ほゆ
(譬喩歌 衣に寄する 巻七の一三一一)
「事なし」は、文字通り事がなく無事であるということだが、くつろげるという意味にここではとるべきであろう。つまり、橡染めは、日常の衣類に多用されていたのである。食べ物でいえば、お袋の味にあたる。この点を踏まえれば、訳は「クヌギ染めの衣は誰もがホッとしてくつろげると言っているのを聞いたその日から・・・私は着てみたいと思っている」となろうか。これを男が女を評した歌として「譬喩」を読み解くと、こうなる。「みんなもいうように、やはり昔なじみの古女房が一番。俺もそろそろ古女房とよりを戻そうか」と。つまり、橡染めとは、古女房のみそ汁のように、男をホッとさせる「おなじみ」なのである。
そこで、冒頭に示した一三一四番歌に、話を戻そう。「解き洗い衣」とは、洗い張りした衣のことである。現在でもそうだが、本格的な着物の洗濯は、洗い張りをするしかない。つまり、縫い糸を解いて洗濯し、仕立て直すしかないのである。それは、例外なく女性の労働であった。すなわち、なじみの橡染めの洗い張りをした衣をむしょうに着たい、と歌っているのである。とすれば「橡の解き洗い衣」を着るというのは、家でゆっくりくつろぐことをいうのであろう。その解き洗いをやってくれるのは、恋人か妻となる。つまり、これを男歌として「譬喩」を読み解くと、「慣れ親しんだ古女房のもとに戻りたいなぁー」ということになろう。
女から女へ、男から女へ、伊勢物語から
もちろん、身分が高く女の召使いがいれば、洗濯という労働を任せることはできた。したがって、洗濯をしたことがないという女性もいたはずである。しかしながら、身分の高い女性も、貧しい男の下に嫁げば、洗濯をしなくてはならなくなる。『伊勢物語』の第四十一段は、姉妹の明暗を分けた物語である。その小道具に洗濯が使われている。一人の女は貧しい男の下に嫁ぎ、一人の女は身分の高い男の下に嫁いだ。十二月ともなれば、正月の参内用の衣装を整えなければならない。この話に切迫感があるのは、実は十二月という季節の設定にあるのである。この点を見逃してはならない。当然、この季節、大祓(おおはらえ)と、それに続く正月行事をひかえて、女たちは洗濯と繕い物に励んだことだろう。しかし、貧しい男に嫁いだ女には、召使いもいない。したがって「手づから」、すなわち自ら洗い張りをしなくてはならない。けれども、洗濯という労働に心得のない女は、男の着るべき緑色の衣の肩の部分を破いてしまう。貧しい家に、代え着などあろうはずもなく、まして正月参内用の衣装・・・まさに絶体絶命である。衣服が身分を表す貴族社会において、これほど惨めなことはない。だから、女は泣くしかなかった。それを聞いた身分の高い男は、緑の着物を探し求めて、贈ってやったのである。しかし、姉妹のこと、援助される側にもプライドというものがある。身分差があればなおさらのことだ。そこで、身分の高い男は、こういう歌を添えたのである。「紫草の根が色濃いときは、まさに野はみどり、他の草木と紫草との区別などつくはずもない。妻を愛する気持ちと、その『はらから』を愛する気持ちとを、区別することなどできやしない。だから貴女を助けるのです・・・遠慮は無用」と。つまり、受け取る相手の気持ちを察した歌を贈ったのである。優しさを表現するには、相手の気持ちを感じ取る感性を磨かなくてはならないのである。
むかし、女はらから二人ありけり。一人はいやしき男のまづしき、一人はあてなる男もたりけり。いやしき男もたる、十二月(しはす)のつごもりに、うへのきぬを洗ひて、手づから張りけり。心ざしはいたしけれど、さるいやしきわざも習はざりければ、うへのきぬの肩を張り破(や)りてけり。せむ方もなくて、ただ泣きに泣きけり。これをかのあてなる男聞きて、いと心ぐるしかりければ、いと清らなる緑衫(ろうそう)のうへのきぬを見いでてやるとて、
むらさきの 色こき時は めもはるに 野なる草木ぞ わかれざりける
武藏野の心なるべし。 (『伊勢物語』第四十一段)
ここで、注意しなくてはならないのは、衣を贈ることで妻の「女はらから」を助けた男の行動である。二人は同母姉妹、絆は強い。だからこそ、苦労している女のことを男も思いやったのであろう。洗い張りに失敗して、途方に暮れる女を男が助けたのは、「女はらから」の心痛を察したからである。
洗濯という労働の技術は、本来女から女へと伝えられたものであろう。しかし、この姉妹は元々身分が高く、それを習得しなかった。だから、女は洗い張りに失敗したのである。けれども、姉妹の絆と、男の思いやりが、窮地を救ったのである。この話の背景にも、女たちの生活史があるのである。これも、洗濯をめぐる愛情物語の一つであろう。
|