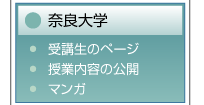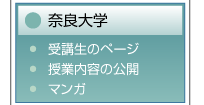君が目を アナタの目を
見まく欲りして 見たくって
この二夜 この二夜は・・・
千年のごとも 千年と思えるほどに
我は恋ふるかも 私は恋焦がれたかもしれない!
(正述心緒歌 巻十一の二三八一)
見ることと、話すこと・・・それは生きること
写真家の土門拳の言葉だったか、こんなことをかつて読んだ。「知性は声にでる。生活は顔色に出る。気迫は目に出る。」と。ならば、『万葉集』においては、「目」はどのように詠まれているのだろうか? 気になるところである。
文武天皇四年(七〇〇)、明日香を名に負う皇女が薨去(こうきょ)する。柿本人麻呂は、その明日香皇女の挽歌を作っている。
・・・御食向ふ 城上の宮を 常宮と 定めたまひて あぢさはふ 目言も絶えぬ・・・
(巻二の一九六)
生前起居されていた宮から、殯宮儀礼が行われる城上宮に運ばれたことを、城上宮を永遠の宮定めて、逢うこともお話になることも無くなった、と述べているのである。「目言」とは、逢って語り合うことであり、それが絶えたということで、皇女の死を表しているのである。また、同じような言い方に「目言離(か)る」(巻十一の二六四七)がある。こちらは、「目言」が離れるということで、別離の表現である。つまり、万葉びとは、「目言」が絶えれば死を意味し、「目言」が離れれば、別離を意味する、と考えていたのであろう。
|